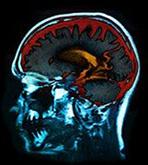|
|
|
|
|
| b-Amyloid(1-42) |
A�����_���X�g���X���Z���~�h�A�R���X�e���[����ӈُ큨�_�o�זE�����A���c�n�C�}�[�a
��-Amyloid(1-42)�ACholesterol |
2004-02-22 17:45:35 ����]�ׂ��Ƃ����u�A���c�n�C�}�[�a���҂�middle frontal gyrus�Ƃ����̈�ɂ́A�R���g���[���ɔ�ׂĂɃR���X�e���[���ƃZ���~�h���~�ς��Ă���v�Ƃ������ʂƂȂ�܂����B 2004�N2��17����PNAS���ɔ��\���ꂽ�������ʂł��Bmiddle frontal
gyrus�̓A���c�n�C�}�[�a�̌����Ƃ����A�����~�ς���ꏊ�̂ЂƂł��B�זE�Ɉ��e����^����_���X�g���X�͎����̕ω��ɔ����Đ����܂��B�܂��C�n�_�o��A���ɖ\�I����Ǝ_���X�g���X�������ăZ���~�h��R���X�e���[�����������܂��B�ȏ���AA�����זE���Ɏ_���X�g���X��^���ăZ���~�h��R���X�e���[����ӂ����Q���A�_�o�זE������ŃA���c�n�C�}�[�a�������N�������ƍl�����܂����B |
|
|
�]�̐_�o�זE���u������ԁv�A���c�n�C�}�[�d�g�݉� |
�V�l���s���i���ق��j�̈�A�A���c�n�C�}�[�a�ɂ��������l�̔]�ł́A�_�o�זE���u������ԁv�ɒǂ����܂�Ď��X�Ɏ���ł������Ƃ��A�c�F��Ɓi�����Ђ�j�E����叕������̌����ŕ��������B�V�������Ö@�̊J���ɂȂ���\��������Ƃ����B�P�U���t�̕ĉȊw���T�C�G���X�Ɍf�ڂ����B���̕a�C�ɂȂ����l�̔]�ɂ��x�[�^�A�~���C�h�Ƃ�������ς��������܂�₷���A�L���Ȃǂɂ������_�o�זE�����ʂ��Ƃ��m���Ă��邪�A�ǂ̂悤�Ɏ��ʂ��͂悭�������Ă��Ȃ��B�c�F����ƕăR�����r�A��Ȃǂ̃O���[�v�́A�_�o�זE�̒��ɂ���~�g�R���h���A�Ƃ����튯�ɒ��ځB�����ɁA�x�[�^�A�~���C�h�Ƃ`�a�`�c�Ƃ����y�f���ꏏ�ɑ��݂��邱�Ƃ��������B������g���Ă��̓���������Ȃ��悤�ɂ���ƁA�_�o�זE�̎��ʊ������啝�Ɍ��邱�Ƃ��킩�����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(2004/04/16) |
|
|
�ψ�APP�܂���A���̔����̓~�g�R���h���A�̃G�l���M�[��ӂ����Q���� |
����ɔ���A�����]�ɒ~�ς���A���c�n�C�}�[�a���f���}�E�X(Tg2576�}�E�X)�ł́AA�����]�ɒ~�ς���O����~�g�R���h���A�̃G�l���M�[��ӂ�זE���Ɋւ���`�q���⏞�I�Ɋ������i���Ă���Ƃ킩��܂����B 2004�N4��28����Hum Mol Genet���ɔ��\���ꂽ�������ʂł��B Tg2576�}�E�X�̃~�g�R���h���A��`�q��͂̌��ʁA�C�n�����������זE�A�C�n�̐��̐_�o�A��]�玿����A���~�ϑO���犈�����i���Ă���Ƃ킩��܂����B�܂�ATPase-6��L���銈�����i��Ԃ̐_�o���I��I�Ɏ_���_���[�W���邱�Ƃ�������܂����B ���̌��ʂ���A�~�g�R���h���A�̃G�l���M�[��ӂ͕ψ�APP�܂���A���̔����ɂ���ď�Q�������A���̌��ʕ⏞�I�Ɉ�`�q���������i����ƍl�����܂����B |
|
|
�A���c�n�C�}�[�a�̌����Ƃ����A���̎_���X�g���X�̓��`�I�j���c��ɂ�� |
2004-11-03 19:44:34 �A���c�n�C�}�[�a�̌����Ƃ����A���̓Ő��́AA�����̃��`�I�j���c��ɂ��_���X�g���X�������ƍl�����Ă��܂��B�q�g��A���ɔ�ׂđ傫�����V�[�g�\��������A�ÏW������b�g��A���y�v�`�h�ł́A�A�~�m�_�z��̈Ⴂ�ɂ�蓺�C�I��Cu(II)���q�g��A�������������ɂ����Ȃ��Ă��܂��B�܂��A���b�g��A���͎_����p���Ȃ��ƍl�����Ă���A���̂��Ƃ���q�g�̓��C�I�������̈悪A���̓Ő��Ɋ֗^���Ă���\������������Ă��܂����B������2004�N10����J Alzheimers Dis���ɔ��\���ꂽ�������ʂ���A���b�g��A�����_����p��L���AA���̎_���X�g���X�̓��`�I�j���̍�p�ɂ��ƍl�����܂����B ���̎����ł́AA���̎_����p�̓r�^�~��E�ɂ���đj�Q����邱�Ƃ�������Ă��܂��B�r�^�~��E�̃A���c�n�C�}�[�a�ɑ����p�͒�܂��Ă��܂��AA�����A���c�n�C�}�[�a�̎�v�Ȍ����ł���Ɖ��肷��ƁA�r�^�~��E�̓A���c�n�C�}�[�a��h����p������Ƃ��������ł��B |
|
|
�A���c�n�C�}�[�a���ǂɔ]���Ǔ����A�~���C�h�~�ς��֗^ |
�č��ł͊��Ґ���450���l�ɏ��Ɛ��v�����A���c�n�C�}�[�a�B�j���[�����i�_�o�זE�j���ӂ̔��i�v���N�j�ɒ~�ς����A�~���C�h-���i�x�[�^�j�y�v�`�h�ƌĂ��`�����A�A���c�n�C�}�[�a���ǂɊ֗^���Ă��邱�Ƃ��m���Ă��邪�A���y�v�`�h�̔]���Ǔ��~�ς����`���Ɋ֗^����Ƃ�2���̐V������������w���uAmerican
Journal of Pathology�v8�����Ɍf�ڂ��ꂽ ��Stony Brook��w��w������������William E. Van
Nostrand����́A��`�q����ɂ��A�A���c�n�C�}�[�a���ljƌn�ɕp�ɂɔF�߂���A���ٓI���A�~���C�h�`���̕ψق������炷�}�E�X���f�����쐬�B�}�E�X���A�~���C�h�`�����Y�����A������]���Ǔ��ɒ~�ρB���̍ۂɁA�����̉��ǂ��������B���̂��Ƃ͐_�o�זE�ł͂Ȃ��]���Ǔ��̒~�ς����ǂ̌����ƂȂ邱�Ƃ��l����ꂽ�B�}�E�X���f���ł͔]�����A�~���C�h�̂ݔF�߂�ꂽ���A���l�Ȃ��Ƃ��A���c�n�C�}�[�a�ł̉��ǂ���тƍs����Q�̌����Ƃ��čl����ꂽ�BVan
Nostrand���́u����̒m���́A�]���̌��ǂ��A���c�n�C�}�[�a�����̏d�v�ȕW�I�ƂȂ邱�Ƃ��������̂��v�Əq�ׂĂ���B2���ڂ̌����́A�č���������iNIA�j�Ȃǂ̌����҂炪���{�������̂ŁA�����x�̔�����э��Z�x���A�~���C�h-�������𗈂��悤���삵���}�E�X2�n����p�����A�A�~���C�h-���������݂��錌�ǂƂ̊W�������B�]���Ǔ��̒~�ς���ɐ_�o�זE���`���������N�����\�����������ꂽ�B�č��A���c�n�C�}�[�a����iAlzheimer's
Association�j�̑�\�Ńg�[�}�X�W�F�t�@�[�\����w�i�t�B���f���t�B�A�j�t�@�[�o�[�_�o�Ȋw������������Samuel
Gandy���m�́u����̌������ʂ��ɗՏ����p�ł���킯�ł͂Ȃ��B�A�~���C�h���~�ς��镔�ʂɒ��ړ��B���Č������邱�Ƃ��ł��Ȃ����߁A���̖��͂���߂ĕ��G�ł���B�܂��_�o�זE�̊Ԃɒ~�ς����A�~���C�h����|���鏈�u���{���͕̂s�\�ł���v�Ǝw�E���Ă���B |
|
|
A���̌��ǓŐ��ŃA���c�n�C�}�[�a���������� |
2005-07-23 00:00:00 A���̔]�̐_�o�ւ̒~�ς̓A���c�n�C�}�[�a�̌����ƍl�����Ă��܂��B���̂��сA�]���ǂւ�A���̒~�ς��A���c�n�C�}�[�a�̔��a�Ɋ�^���Ă��邱�Ƃ�����2�̓Ɨ������������ʂ�8����American
Journal of Pathology���ɔ��\����܂��B1�ڂ̕�Miao���́AA���͍ŏ��]���ǂɒ~�ς��A����A���̒~�ς��}�E�X�̐_�o���ǂɊ�^���Ă���炵���ƌ��_���Ă��܂��B 2�ڂ̕�Kumar-Singh���́A���Z�x��A���ō\������鍂���x�v���[�N�����}�E�X�̎������ʂ\���Ă��܂��B���̎����ɂ��ƁA�����x�v���[�N�͔]���ǂɌ`������A���ǂ⌌�t�]�֖傪�j��AA�������Ǖǂ��痬�o���Č��ǂ̋߂��ɏW�ς��܂����B���Ȃ킿�AA���̓Ő��Ō��Ǔ���̓��ꐫ�������A��Q�����������ǂ̎��ӂ�A�����~�ς��A���̌��ʃA���c�n�C�}�[�a�̌����ƂȂ�]������������ƍl�����܂����B Impaired clearance of amyloid-beta causes vascular damage in
Alzheimer's disease / EurekAlert |
|
|
���C���̃|���t�F�m�[���̓A���c�n�C�}�[�a�̌����ƍl������A���̐_�o�Ő����ɘa���� |
2005-11-14 00:00:00 �u�h�E���̃x���[�ށA�u�h�E����o���郏�C���A�s�[�i�c�ȂǂɊ܂܂��V�R�̃|���t�F�m�[���E���X�x���g�����iResveratrol�j�́A�A���c�n�C�}�[�a�̌����ƍl������A���̓Ő����ɘa�����p������ƕ�����܂����B �_�o�����͂ރO���A�זE�Ɉˑ����āA�a���`�����͐_�o��ϐ�������Ƃ����������ʂ��W�ς��Ă��܂��B�����̌��ʁAIkappaBalpha�j�Q�܂Ń}�C�N���O���A��NF-�ȃ��V�O�i�����O��j�Q����Ɛ_�o�Ő����}������܂����B�܂��A�}�C�N���O���A��A���Ŏh������ƁANF-�ȃ��o�H�߂���RelA/p65�̃A�Z�`���������i����܂����B SIRT1�E�A�Z�`�����y�f���ߏ蔭����������ASIRT1�A�S�j�X�g�ł���Resveratrol�𓊗^����ƁAA���̎h���ɂ��NF-�ȃ��V�O�i���`�B�������ɒቺ���A���͂Ȑ_�o�ی��p�������炳��܂����B �ȏ���A�}�C�N���O���A�זE�ɂ�����NF-�ȃ��V�O�i�����O��A���ɂ��_�o�זE���Ɋ֗^���Ă���ASIRT1�́ANF-�ȃ��V�O�i�����O�j�Q�ɂ��~�N���O���A�ˑ��I��A���̐_�o�Ő���}������ƕ�����܂����B |
|
|
�A���c�n�C�}�[�a�̌��������A��v�\���̉𖾂ɐ��� |
�A���c�n�C�}�[�a�̌����Ƃ���邽��ς����u�x�[�^�E�A�~���C�h�v�̎�v�\�����Ƃ炦�邱�ƂɁA����a���E����H�w�����ȏ�������̃O���[�v�����E�ŏ��߂Đ��������B�P�T���A���{���ł̃V���|�W�E���Ŕ��\�����B���쏕�����́u���̎�v�\�����ω�����ƁA�x�[�^�E�A�~���C�h�����X�Ɛ��ۏ�Ɍł܂��Ă����A�a�C�������N�����v�Ɛ����B���̕ω���h����������������A���Ö�ɂȂ���Ɗ��҂��Ă���B�x�[�^�E�A�~���C�h�́A���ۏ�Ɍł܂�₷���������Ђ����A�\����͂ɓK����������Ԃɂ���̂���������B���쏕������́A���ۉ��ɊW����ƌ����Ă��镔�����A�\�����͂ɓK�����ʂ̂���ς����ɑg�ݍ��ގ�@�ŁA�G�b�N�X���ɂ���͂ɐ����B���̕������܂��܂�ĕ��ʏ�ɂȂ����`�����Ă���A���ɕ�������ɂ����\���ł��邱�Ƃ����������Ƃ����B�@�x�[�^�E�A�~���C�h�́A����Ȕ]�ł͍y�f�ɂ���ĕ�������邪�A�����ł��Ȃ��Ȃ�ƁA�~�ς��āu�V�l���v�Ƃ������ۏ����`���A�A���c�n�C�}�[�a�������N�����ƍl�����Ă���B �i�ǔ��V���j
- 11��16��3��14���X�V |
|
|
BMI�E�̎��b�ƌ�����A��42���x���ɗL�ӂȑ��ւ��F�߂�ꂽ |
2006-01-03 00:00:00 �얞�⑾��߂��̓A���c�n�C�}�[�a�̃��X�N�����߂܂��B����l18�l��Ώۂɂ��������̌��ʁA�A���c�n�C�}�[�a�̌����̈�ƍl�����Ă���^���p�N���EA��42�̌��������x����BMI�E�̎��b�ɗL�ӂȑ��ւ��F�߂��܂����BA��42�͂��a�����̍�������A���ł��BA��42�Ƃ̑��ւ͔F�߂��܂������A���a�������Ⴂ�Z��A���EA��40��BMI�E�̎��b�ɑ��ւ͔F�߂��܂���ł����B |
|
|
�w���ւ�A���������A���c�n�C�}�[�a�ɂ����ďd�v�Ȗ������ʂ����Ă��� |
2006-03-16 00:00:00 ���A�~���C�h�iA���j�̓A���c�n�C�}�[�a�iAD�j�̌����ƍl�����Ă��܂����AA���ɂ��_�o�ϐ��̃��J�j�Y���͕������Ă��܂���B����܂łɁAA���͒��߃w���Ɍ������ċ@�\�I�w�������������N�����A���̌���AD�ɂ����ďd�v�ȍזE�ω���������Ƃ�������������Ă��܂��B���̉�����Children's Hospital Oakland Research Institute��Hani Atamna�������\���܂����BAtamna���́A�w�������ɂ��A�w�����܂�complex IV���������ă~�g�R���h���A����ߎ_�����f�Ȃǂ̎_�������̕��o���N���邱�Ƃ��m�F���Ă��܂��B���̂���Atamna���́Ain vivo�ɂ����āA���߃w���ւ�A��������A���ɂ��w�����R�̃��J�j�Y���ł��邱�Ƃ������X�Ȃ�G�r�f���X��2��28����PNAS���ɔ��\���܂����B�܂��A�זE�t���[�V�X�e���ɂ����āA�w����A���Ɍ������AA��-�w�������̂���邱�Ƃɂ��A���̋ÏW��h���܂����BAtamna���́A����A��-�w�������̂����߃w��������������ƍl���Ă��܂��B���̌��ۂɂ��AA���ɂ���Đ_�o��זE��זE�̃w�������ƓS����荞�݂��㏸���邱�Ƃ������ł��܂����B�܂��AA��-�w�������̂̓y���I�L�V�_�[�[������L���邱�Ƃ�������A�ߎ_�����f�ɂ���Z���g�j����3,4-�W�q�h���L�V�t�F�j���A���j���̎_����G�}���܂����BAD�̃��f���}�E�X�̔]�ɂ����Ď_��������}������N���N�~���́A���̃y���I�L�V�_�[�[��j�Q���܂����B�ȏ���A�w���ւ�A���������N�_�Ƃ��āAA���ɂ��w�����R�A���啪�q�̎_�������A����̐_�o�`�B�����̌����Ƃ���3�̌��ۂ��ł���ƍl�����܂����B |
|
|
���A�~���C�h1-40�����A�~���C�h1-42�̌������Z�x�͔F�m�ǂ̃��X�N�Ɗ֘A���Ă��� |
2006-07-26
���A�~���C�h(A��)�y�v�`�h�̓A���c�n�C�}�[�a�Ɍ�����v���[�N�̎�v�����ł��B���A�~���C�h1-40�ƃ��A�~���C�h1-42�̌������Z�x�͔N��ƂƂ��ɏ㏸���܂����A��N���A���c�n�C�}�[�a�̌����ƂȂ�ψق̂���l�ł͂��̔Z�x���������܂��B�܂��A�F�m�ǃv���Z�X�̏����Ƀ��A�~���C�h1-42�̔Z�x���ቺ����\��������܂��B�����2��A���̔Z�x���F�m�ǂ̃��X�N�ƊW����Ɖ��肵�A�O�����P�[�X�R�z�[�g�����ł��̉�������������ʂ�2006�N8����Lancet
Neurol���ɔ��\����Ă��܂��B����ג��o�����F�m�ǃ��X�N�̂���팱��1756���̂����A392��������8.6�N�̃t�H���[�A�b�v���Ԓ��ɔF�m�ǂǂ��܂����B��������A���Z�x�ƔF�m�ǂ���т��̃T�u�^�C�v�Ƃ̊W���R�b�N�X���n�U�[�h���f����p���Ē������܂����B�����̌��ʁA�x�[�X���C���ɂ����鍂�Z�x��A��1-40�ƔF�m�ǃ��X�N�̍����ɂ͊֘A������܂������AA��1-42�̔Z�x�͊֘A���Ă��܂���ł����BA��1-40�Z�x�̑�1�l���ʁiA��1-40�Z�x���ł��Ⴂ�O���[�v�j�Ɣ�r����ƁA��2�E��3�E��4�l���ʂ̔F�m�NJ댯���i�n�U�[�h��j�͂��ꂼ��1.07�A1.16�A1.46�ł����BA��1-42/A��1-40�䂪�����l�ł͔F�m�ǃ��X�N���ቺ���܂����BA��1-42/A��1-40��̑�1�l���ʁiA��1-42/A��1-40�䂪�ł��Ⴂ�O���[�v�j�Ɣ�r����ƁA��2�E��3�E��4�l���ʂ̔F�m�NJ댯���i�n�U�[�h��j�͂��ꂼ��0.74�A0.62�A0.47�ł����B�A���c�n�C�}�[�a�Ɣ]���ǐ��F�m�ǂɂ��Ă����l�̊֘A�������܂����B�ȏ�̌��ʂ���AA��1-40�̌������Z�x�������ꍇ�ɁA�F�m�ǃ��X�N�������Ȃ�Ƃ킩��܂����B���ɁAA��1-40�̌������Z�x��������A��1-42�̔Z�x���Ⴂ�ꍇ�ɔF�m�ǃ��X�N�������Ȃ�܂����BA���̌������Z�x��F�m�ǔ��ǂ̃}�[�J�[�Ƃ��ė��p����\����T�鉿�l������Ǝv���܂��B�d>
Article�@Plasma A��1-40and A��1-42 and the risk of dementia: a prospective
case-cohort study : Lancet Neurology 2006; 5:655-660 |
|
|
�L�̔]���ł��V���ɔ�����A���������_���^�E���~�ς��� |
2006-12-10 �ȑO����l�R�i�L�j�͔F�m�ǂ������邱�Ƃ��m���Ă��܂������A�V���Ȍ�������A�L�̔F�m��Q�ɂ��ǂ����A���������_���^�E���֘A���Ă���炵���ƕ�����܂����BA���������_���^�E�̒~�ς̓q�g�̃A���c�n�C�}�[�a�̌����ƍl�����Ă��錻�ۂł��B�܂��A�����̕����͉���ɂ��]���ɒ~�ς��܂��B�_�o�@�\��Q��悷��17�C�̔L���܂ސ���16�T�`14��19�C�̔L�̔]�ׂ����ʁA�L�ł�����ɂ���Ĕ]����A���������_���^�E���~�ς���ƕ�����܂����BEdinburgh University��Danielle Gunn-Moore����J Feline Med Surg���ɔ��\�����������ʂł��B |
|
|
�j���z����������������ƊC�n�ƝG���̂ł�A���̒~�ς����i���� |
2006-12-23 �ŋ߂̌����ŁA�j���̉���ɔ���������e�X�g�X�e���������̓A���c�n�C�}�[�a�̃��X�N�t�@�N�^�[�ƕ������Ă��܂��B�������A���h���Q���̌������A���c�n�C�}�[�a�̔����ɂǂ̂悤�ȉe����^����̂��͕s���ł����B�V���Ȍ����̌��ʁA�A���c�n�C�}�[�a���f���}�E�X�i3xTg-AD�j���琫�B��E�o����ƊC�n�ƝG���̂ɂ����ăA���c�n�C�}�[�a�̎�v�Ȍ����Ɩڂ���Ă���^���p�N���EA���̒~�ς����i����ƕ�����܂����BA�����x���㏸�ƕ��s���āA���B�E�o�����}�E�X�ł͊C�n�@�\�̏�Q����������s���ω����F�߂��܂����B�d�v�Ȃ��ƂɁA���B�E�o����3xTg-AD�}�E�X���A���h���Q���E�W�q�h���e�X�g�X�e�����Ŏ��Â����A���~�ςƍs�����Q���y�����܂����B���̌��ʂ���A�A���h���Q������������ƃA���c�n�C�}�[�a�l�_�o�a���̔��B�����i���邱�Ƃ��ؖ�����A���l�̃��J�j�Y������e�X�g�X�e�����j���̃A���c�n�C�}�[�a�̃��X�N�㏸�̊�b�𐬂��Ă���Ǝ�������܂����B����ɁA����̌��ʂ��獂��j���̃A���c�n�C�}�[�a�̎��Â�\�h�ɃA���h���Q���x�[�X�̃z��������[�Ö@���L�p�ƍl�����܂����B |
|
|
�v���I���^���p�N���́A�A���c�n�C�}�[�a�̌����ƍl�����Ă���A���̐����߂������������ |
2007-07-10 -
���Z�N���^�[�[�EBACE1�ɂ��A�~���C�h�O��̃^���p�N�iAPP�j�̕����́A�A���c�n�C�}�[�a�̕a���Ɋ֗^���Ă���A���y�v�`�h�̐����̏����X�e�b�v�ƂȂ��Ă��܂��B |
|
|
�A���c�n�C�}�[�a��A���a�����Γ���ł��F�߂���`A���W�I��ŗΓ��Ⴊ���Â����� |
2007-08-09 -
A�������A�_�o�זE���A�זE�����̓A���c�n�C�}�[�a�Ƌ����֘A���邱�Ƃ��������Ă��܂��B�V���Ȍ����̌��ʁA���l�̃��J�j�Y�����Ԗ������E�Γ���ɂ����Ă��F�߂���ƕ�����܂����BBiotoday |
|
|
�A���c�n�C�}�[�a�F���������̒~�ϗ}����y�f���� |
�A���c�n�C�}�[�a�̌����ƂȂ邽��ς����u�A�~���C�h�x�[�^�v���]�ŕ������ꂸ�ɒ~�ς���̂�}���镨�����A���o�C�I�T�C�G���X�������Ȃǂ̌����`�[���������A�Q�U���t�̕ĉȊw�A�J�f�~�[�I�v�ɔ��\�����B���̕����́A�����𑣂��z�������u�v���X�^�O�����W���c�Q�v�����o���y�f�B�`�[���́u���̍y�f���\���ɓ����Ȃ��Ȃ�ƁA�A���c�n�C�}�[�a�ǂ���\�������܂�Ɨ\�z�����v�Ƙb���B���̍y�f�͔]�Ґ��i���������j�t�̒��ɕ��傳��Ă���B�����ŁA���̍y�f���u�A�~���C�h�x�[�^�v�ɉ�����ƁA���҂��������т��A�A�~���C�h�x�[�^���m���ÏW���Ȃ��Ȃ����B�}�E�X�̈�`�q�����ς����̍y�f��ł��Ȃ��悤�ɂ���ƁA����ȃ}�E�X�ɔ�ׁA�]���A�~���C�h�x�[�^�~�ϗʂ��R�{�ɑ������B�t�ɍy�f�̕���ʂ𑝂₵���}�E�X�́A�A�~���C�h�x�[�^�~�ϗʂ������̂P�ɂȂ����Ƃ����B�A���c�n�C�}�[�a�͔F�m�ǂ̑�\�I�ȕa�C�ŁA�����̊��Ґ��͖�Q�O�O���l�Ƃ����B�y�i�R�x�q�z |
|
|
�����ɖL�x�ȃI���K-3���b�_�̓A���c�n�C�}�[�a�}�E�X�̕a�ς��y������ |
2007-04-19 -
A���ƃ^�E�a�ς������A���c�n�C�}�[�a�}�E�X�i3xTg-AD�j�ɃI���K-3���b�_�E�h�R�T�w�L�T�G���_�iDHA�j�𓊗^����ƁA�n��A���ƃ^�E���x�����ቺ���邱�Ƃ��m�F����܂����B
Biotoday |
|
| Tau |
A���ɑ���R�̂�A���̋ÏW�ƂƂ���Tau�^���p�N���̋ÏW�������ł��� |
2004-08-06 20:25:33 A���ɑ���R�̂��C�n�ɓ��^����ƁA�A���c�n�C�}�[�a�̌����Ƃ����A���̋ÏW��3����ɏ������A����ɂ���2�����Tau�^���p�N���̋ÏW�������Ă����Ƃ킩��܂����B
2004�N8����Neuron���ɔ��\���ꂽ�������ʂł��B �܂�A���ɑ���R�̂𓊗^����30����ɂ�A���̋ÏW���F�߂��܂������ATau�^���p�N���̋ÏW�͂����܂���ł����B���̂��Ƃ���ATau�^���p�N���̋ÏW�͕a�C�����i�s������Ԃł����錻�ۂƍl�����܂����B
�܂��ATau�^���p�N���̓v���e�A�\�[������ĕ�������A�ߓx�Ƀ����_�����ꂽTau�^���p�N���͕�������܂���ł����B�d> News
Source+ Hope for an Alzheimer's vaccine / BBC |
|
|
�A���c�n�C�}�[�a�̋L���ɐV���ȃA�v���[�` |
�~�l�\�^��w�̌����ǂ́A�A���c�n�C�}�[�a�ɂ��L����Q���A�^�E�ƌĂ��^���p�N���̔����j�~�ɂ���ĉ��P�ł��邱�Ƃ��}�E�X�̎����Ŏ������B�A���c �n�C�}�[�a���҂̔]�ɂ݂���^�E���܂_�o�����ەω��i�^���p�N�������܂����\�����j�́A�������̋@���Ɋւ��ƍl�����Ă���B�����ǂ́A�_�o���� �ەω�����}�E�X����`�q����ɂ���č쐬���A����ɓ���̖�ܓ��^���^�E�̈�`�q�������j�~�����悤��`�q���삵���B�����̃}�E�X�ɋL���e�X�g ���s���ƁA����ȃ}�E�X�����L���͂��Ⴉ�������A��܂��^�E�̔�����j�~����ƋL���͂������B����A�^�E������j�~���Ă��_�o�����ەω��͐i�s���������B�����ǂ́A�^�E���_�o�����ەω��Ƃ͊W���Ȃ��@���ŋL����Q�Ɋ֗^���Ă���A�^�E�̋@�\��j�Q������@�����Ö@�Ƃ��Č����ΏۂƂȂ�\�������� �ƍl�@�����B |
|
|
�y�x�F����Q�iMCI�j���҂̔]���t�����^�E��A���Z�x�̓A���c�n�C�}�[�a�̔����ƒ��ڊ֘A���Ă��� |
2006-02-08 00:00:00 �y�x�F�m��Q�i�y�x�F����Q�AMCI�j����137�l�ƌ���{�����e�B�A137�l��Ώۂɂ���4-6�N�Ԃ̒ǐՒ����̌��ʁAMCI���҂������A���c�n�C�}�[�a�ɂȂ郊�X�N�Ɣ]�Ґ��t���̑S�Ă��^�E�A�����_���^�E�AA��42�̔Z�x�͗L�ӂɑ��ւ���ƕ�����܂����BThe Lancet
Neurology����2006�N2��7���̃I�����C���o�[�W�����ɔ��\���ꂽ�������ʂł��B |
|
|
�^�E�ɂ��_�o�ϐ���h�����������肳�ꂽ |
2006-09-17 �A���c�n�C�}�[�a���܂ސ_�o�ϐ������ɂ����āA�^�E���܂ސ_�o�����ەω��i�_�o�����۔Z�k�́j���F�߂��܂��B�A���c�n�C�}�[�a���҂̐_�o�ϐ��E�F�m�@�\�ቺ��NFT�ʂ����ւ��܂����A�^�E�ɂ���ėU�������_�o�ϐ���\�h���郁�J�j�Y���͖w�Ǖ������Ă��܂���ł����B�V���E�W���E�o�G�ƃ}�E�X�̔]�̕����̈�̈�`�q������͂���A���x�ɕۑ����ꂽ�^���p�N���Epuromycin-sensitive aminopeptidase (PSA/Npepps) ���܂ރ^�E���ߕ��������肳��܂����B���̌������ʂ�2006�N9����Neuron���ɔ��\����Ă��܂��BIn vivo�̎�������A�^�E�ɂ���ėU�������_�o�ϐ���PSA�͖h���APSA�@�\������������Ɛ_�o�ϐ����������܂����B����Ȃ��������A�q�gPSA���^�E�ړI�Ƀ^���p�N����������ƕ�����܂����B���̌��ʂ���A���肳�ꂽPSA�₻�̑��̈�`�q�́A�^�E�I�p�`�[�̎��Ã^�[�Q�b�g�Ƃ��ėL�]�ƍl�����܂����B |
|
|
�F�m�ǂ̌����̂ЂƂH�@�ُ킽��ς����̐��̉� |
�l�i���ς������A�ُ�s�����Ƃ����肷�邱�Ƃ������F�m�ǂ̈��A�u�O�������^�F�m�ǁv�i�e�s�c�j�̌����Ƃ݂���ُ킽��ς����̐��̂��A�����s���_��w�����������̃O���[�v���˂��~�߂��B�R�O�����瓌���s���ŊJ�������{�_�o�a���w��Ŕ��\����B�a�C�̃��J�j�Y���̉𖾂⎡�Ö@�J���ɂȂ���\��������B �e�s�c�́A�U�T�Έȉ��̔F�m�ǂƂ��Ă̓A���c�n�C�}�[�a�Ɏ����ő����B�e�s�c�́A�]�ɁA�^�E�Ƃ�������ς��������܂�^�C�v�ƁA�^�E�ȊO�̂���ς��������܂�^�C�v�ɕ������邪�A�^�E�ȊO�̂���ς����̐��͕̂������Ă��Ȃ������B ���J�쐬�l�`�[�����[�_�[�ƐV��N����C��������́A���҂̔]�Ɉُ�ɂ��܂��Ă��镨�����ڂ������ׁA�s�c�o�S�R�Ƃ��邽��ς����ł��邱�Ƃ�˂��~�߂��B���̂���ς����́A�ؓ�������ɓ����Ȃ��Ȃ�؈ޏk�i�����キ�j�������d���ǁi�`�k�r�j�̊��҂̐Ґ��i���������j�ɂ����܂��Ă��邱�Ƃ��������B�č��O���[�v���������_�\���Ă���B �A���c�n�C�}�[�a�ł́A�A�~���C�h�x�[�^�Ƃ����ُ킽��ς��������܂邱�Ƃ��˂��~�߂��Ă���A�����W�I�Ƃ��鎡�Ö@�̊J�����i��ł���B����̐��ʂ����Ö@�̊J���ɂȂ���\��������B �і��M�s�E�����w�������]�Ȋw���������Z���^�[�a����`�q�����O���[�v�f�B���N�^�[�̘b�@�`�k�r�ƔF�m�ǂ̎d�g�݂��ǂ̂悤�ɊW����̂��A�V���Ȍ��������W���������B Asahi,Com |
|
|
�V�l����_�o�����ەω��Ɍ�������ᕪ�q�������EFDDNP��p����PET�X�L�����ŃA���c�n�C�}�[�a�����ʂł��� |
2006-12-21 �A���c�n�C�}�[�a�̃��X�N������y�x�F�m��Q���҂̔]�̔玿�̈�ɒ~�ς����A�~���C�h�V�l���iAmyloid senile plaque�j���^�E�_�o�����ەω��itau neurofibrillary tangle�j�̓A���c�n�C�}�[�a�̐_�o�a���w�I�����ƂȂ��Ă��܂��B�����ُ̈�^���p�N�����N�P�I�Ɍ��o������@�͐f�f���܊J���Ŏg�p����T���Q�[�g�}�[�J�[�̊J���ɂ����ėL�p�ƍl�����܂��B�A�~���C�h�V�l�����^�E�_�o�����ەω��Ɍ�������ᕪ�q�EFDDNP���L���ɖ�肪����Ǝ��Ȑ\������83�l�̔팱�҂ɒ��˂������PET�X�L�����iFDDNP-PET�j�����{���AFDDNP�̌����ŃA���c�n�C�}�[�a���҂����������邩�ǂ������������������̌��ʂ�2006�N12��21����NEJM���ɔ��\����Ă��܂��B���̎����̌��ʁAFDDNP�̌����l�̓A���c�n�C�}�[�a���ҁA�y�x�F�m��Q���ҁA����l�ŗL�ӂɈقȂ��Ă��܂����BFDDNP�̌����l���ł����������̂̓A���c�n�C�}�[�a���҂ŁA���̎��ɍ��������̂͌y�x�F�m��Q���ҁA����l�ł�FDDNP�̌����l���ł��Ⴍ�Ȃ��Ă��܂����B���̌��ʂ���A�A���c�n�C�}�[�a���҂ƌy�x�F�m��Q���҂�L���Ă��Ȃ��l�ƌy�x�F�m��Q���҂�FDDNP-PET�Ŏ��ʂ�����ƍl�����܂����B �d>
Article�@PET of Brain
Amyloid and Tau in Mild Cognitive Impairment. NEJM. Volume 355:2652-2663
December 21, 2006 Number 25 |
|
| �\�}�g�X�^�`�� |
�A���c�n�C�}�[�F��������ς����A���𑣂���������@���� |
�����w�������̌����`�[���́A�A���c�n�C�}�[�a�̌�������ς���������y�f�̓��������߂鐫�����u�\�}�g�X�^�`���v�ɂ��邱�Ƃ�˂��~�߁A�Q�O���t�̕ĉȊw���u�l�C�`���[�E���f�B�V���v�i�d�q�Łj�ɔ��\�����B�\�}�g�X�^�`���́A�����z�������̕���𐧌䂷�邽��ς����B���̕������זE�\�ʂ̎�e�̂Ɍ��т��ƁA�]���̕����y�f�������A�a�C�̌�������ς������������i�����Ƃ����B���Ƃ��Ƒ̓��ɂ��镨���̂��ߕ���p�̏��Ȃ����Õ����Ƃ��Ē��ڂ��ꂻ�����B�@�A���c�n�C�}�[�a���x�[�^�A�~���C�h�ƌĂ�邽��ς������]���ɒ����������ʁA�_�o�זE�����ł��A�]���ޏk�i�����キ�j����ƍl�����Ă���B�\�}�g�X�^�`���̔]���̗ʂ́A����ƂƂ��Ɍ������邱�Ƃ��������Ă����B�@�����`�[���́A�\�}�g�X�^�`�������Ȃ������}�E�X�ׂ����ʁA�A�~���C�h������y�f�u�l�v�����C�V���v�̔]���̗ʂ��ʏ�}�E�X�̂U���܂Ō��邱�Ƃ��m�F�����B�܂��A���̃}�E�X�̔]�ɂ��A�~���C�h�̒�������T�������������B�@�����`�[���͂O�R�N�A�a�����̂Ȃ��E�C���X�Ƀl�v�����C�V���̈�`�q��g�ݍ��݁A�A�~���C�h���������₷���}�E�X�̔]�ɒ��������`�q���Â��{���A�A�~���C�h�̒����}���ɐ��������B�������A��`�q���Â͎����܂Ŏ��Ԃ������邽�߁A�����`�[���͖�܂ɂ���ăl�v�����C�V���̓��������߂鎡�Ö@�J���Ɏ��g��ł����B�@�����`�[���̐������b�E�_�o�`���i����ς��j���䌤���`�[�����[�_�[�́u�\�}�g�X�^�`���̎�e�̂ɓ�����܂��J���ł���A�O�ȓI�Ȏ��Â╛��p�̐S�z�Ȃ��A�~���C�h�̒��������点��B���p���̉\���͍����v�Ƙb���B�y�i�R�x�q�z |
|
|
�A���c�n�C�}�[�\�h�Ɍ��@�����A�}���̎d�g�݉� |
�A���c�n�C�}�[�a�̔��ǂ�i�s��x�点��y�f���]���Ŋ���������d�g�݂𗝉��w�������E�]�Ȋw���������Z���^�[�i��ʌ��a���s�j�̃`�[�����}�E�X���g���������ʼn𖾁A20���t�̕Ĉ�w���l�C�`���[���f�B�V���d�q�łɔ��\�����B�@���̍y�f�́u�l�v�����C�V���v�B�A���c�n�C�}�[�a�̌��������x�[�^�A�~���C�h���A�]�ł̒~�ς�h���B����̌��ʂɂ������̉��w�����ł��̍y�f���������ł���\���̂��邱�Ƃ�������A�\�h�@�J���Ɍ��ѕt���������B�@�`�[���͐_�o�`�B�����̈��A�\�}�g�X�^�`���������Ȃ��}�E�X�̔]�ł̓l�v�����C�V���̊�����������A�x�[�^�A�~���C�h��1.5�{�ɑ����邱�Ƃ��B�����̌����\�}�g�X�^�`���������Ă��邱�Ƃ��𖾂����B�@�\�}�g�X�^�`���Ɠ�����������������̉��w�����͕�������A���̂�����1�́A�قڔ]�̍זE�����œ����A�ق��̑����g�D�ł͓����Ȃ����߁A����p�������邱�Ƃ��ł��������Ƃ����B�@�������b�i�����ǂ��E�������݁j�`�[�����[�_�[�́u�\�}�g�X�^�`���͔N�����ɂ�Č��邱�Ƃ��m���Ă���B���ꂪ����ɂȂ��ăA���c�n�C�}�[�a�����ǂ��錴����1�ł͂Ȃ����v�Ƙb���Ă���B�L���F�����ʐM�� |
|
| �C���X���� |
�`�C���X�����l�Ɖ��ǃ}�[�J�[�̏㏸�`�@�A���c�n�C�}�[�a�̕a���� |
�k�j���[���[�N�l
���V���g����w�i���V���g���B�V�A�g���j�_�o�Ȋw��Mark A. Fishel���m��́C�C���X�������x���̒����x�̏㏸�����ǃ}�[�J�[����-�A�~���C�h�������C�A���c�n�C�}�[�a�iAD�j�̕a���ƂȂ��Ă���Ƃ��錤�����ʂ�Archives
of Neurology�i2005; 62:
1539-1544�j�ɔ��\�����B�_���̔w�i���ɂ��ƁC�C���X������R���ƍ��C���X�������ǂł͉��ǃ}�[�J�[���������Ă���CAD���X�N���㏸���Ă���B���ǂ�AD�̌��ƂȂ�a���Ƃ��鉼��������Ă���B�@�����m��́C55�`81�̌��퐬�l16��ɑ��āC���파���l���ێ�������ԂŌ����C���X�������x�����㏸�����C�����Ɣ]�Ґ��t���̉��ǃ}�[�J�[�C���W�����[�^����-�A�~���C�h���x���̕ω��𑪒肵���B���̌��ʁC�����x�̍��C���X�������ǂɂ�蒆���_�o�n�̉��ǃ}�[�J�[�������ɏ㏸���Ă����B����̏����͐^�����A�a�⍂�����Ȃǂ��C���X������R�����C�ꕔ���C���X�����U�����ǂ����AD���X�N���㏸�����邱�Ƃ��������Ă���B���̃��f���͐^�����A�a�Ɋ֘A�������̂ł��邪�C���A�a�ɂ͜늳���Ă��Ȃ����얞��ϓ��\�̒ቺ�C�S���ǎ����C��������L���鐬�l�̑����ɂ����āC���C���X�������ǂ��C���X������R���͖������Ă���B����̌��ʂ́C�����N�W�c�ɂ����邱���̎����̗��s���CAD�̌��I�Ȝ늳���̏㏸�������N�����\���ɒ��ӂ𑣂����̂ł���BAD�̕a���ɂ������C���X�����̖����𗝉����邱�Ƃ́CAD�̎��ÁC�i�s�x���C����ɗ\�h�Ɍ����C���L���Ȑ헪�̊J���ɂȂ��邱�Ƃ����҂����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�iCopyright
2005 DoctorsGuide.com�j |
|
|
�A���c�n�C�}�[�a���i�s����ɂ�Ĕ]�����C���X������e�̃��x�����C���X�����ɑ����C���X������e�̂̊����ቺ���� |
2005-12-05 00:00:00
����ɉ�����l�Ɨl�X�Ȓi�K�̃A���c�n�C�}�[�a�iAD�j���ҍ��v45�l�̎���]��p������͂ŁuAD���i�s����ɂ�Ĕ]���̃C���X������e�̃��x���ƃC���X�����ɑ���C���X������e�̂̊����ቺ����v�Ƃ������ʂ������܂����BRhode
Island Hospital��Suzanne M. de la Monte����Journal of Alzheimer's
Disease��11�����ɔ��\�����������ʂł��B�ł��i�s�����A���c�n�C�}�[�a���҂̔]���ł́A����Ȑl�̔]�ɔ�ׂăC���X������e�̂̃��x����80%�߂��ቺ���Ă��܂����B�܂��A�C���X�����ƃC���X�����Ɋ֘A���������EIGF-I�̓R�����A�Z�`���g�����X�t�F���[�[�iChAT�j�̔����𑣐i���邱�Ƃ�������܂����BChAT�́AAD�ŕs������A�Z�`���R�����̐����ɕK�v�ȍy�f�ł��B���N���߂�de
la Monte���́A�C���X������IGF I/II�͔]���ō���A�����̒ቺ�͐i�s����AD�Ɋ֘A���邱�Ƃ��m�F���Ă��܂��B |
|
|
�A���c�n�C�}�[�a�͓��A�a�̗ގ����� |
�A���c�n�C�}�[�a���i�W����ɂ�āA�]���ł̍זE����_�o�����ەω��ȂǁA���̌������𖾂���Ă��Ȃ����������̑����́A�]�����C���X�����Y���\�̒ቺ�Ȃ��C���X�������`�B�ُ̈�ɋN������Ƃ����������ʂ��A��w���uAlzheimer's
Disease�v11�����Ɍf�ڂ��ꂽ�B���̂��Ƃ���A�A���c�n�C�}�[�a���_�o�����厾���Ƃقړ������̂��A���邢�͕ʂ̃^�C�v�̓��A�a�ł��邱�Ƃ��l������Ƃ����B
�ă��[�h�A�C�����h�a�@�̐_�o�a���w�҂Ńu���E����w��w���a���w������Suzanne M. de la Monte����́A�]�ł��C���X�����Y���ƁA�A���c�n�C�}�[�a���҂ł͂��̐��Y�\���ቺ���Ă��邱�Ƃ���Ă��邪�i�R���V���t����j�A����͂���ɁuBraak�a���iBraak
Stages�j�v�Ɋ�Â��āA�قȂ�a���ɐf�f���ꂽ�A���c�n�C�}�[�a����45�Ⴉ�琶���Ŕ]�g�D���̎悵�A�A���c�n�C�}�[�a�ǂ��Ă��Ȃ��l����̎悵���g�D�W�{�Ɣ�r�����B
�A���c�n�C�}�[�a�Ŏ�ɑ����𗈂��O���t���C���X�����l������C���X������e�̂̋@�\��]�������Ƃ���A�A���c�n�C�}�[�a�����i�K�Ŕ]�����C���X�����l�Ƃ���Ɋ֘A����זE��e�̗̂ʂ��}���ɒቺ���A�d�Ǔx���i�ނɂ�A�C���X�����l���ቺ�������邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B�܂��A�A���c�n�C�}�[�a�̎w�W�ƂȂ��A�Z�`���R�����l�̒ቺ���A�C���X�����l�̌������C���X�����l�������q�̋@�\�ቺ�ɒ��ڊ֘A���邱�Ƃ����������B �a�����ł��i�W�����i�K�ł́A�C���X������e�̂�����]�ɔ�ז�80���ቺ���Ă����B�����ɉ����āA�C���X�������C���X�����l�������q-I���זE��e�̂Ɍ�������\�͂������邱�ƂȂǂ��A�זE���ɂȂ��邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B
de la
Monte���́u�F�m�\�͂Ɋւ��_�o�`�B�����A�G�l���M�[��ӂ̒ቺ�A�i�s���̓����ł���_�o�����ەω��������炷�ُ�ȂǁA����̌������ʂ́A������������̊T�O���P�ɂ܂Ƃ߁A�A���c�n�C�}�[�a���܂��Ɂh�R�^���A�a�h�ƌĂԂ��Ƃ��ł�����̂ł��邱�Ƃ������Ă���v�Ƃ����B
�ăC���f�B�A�i��w������Z���^�[�A�A���c�n�C�}�[�a�E�_�o���_�����Z���^�[�����㗝�Ő��_��w������Hugh C. Hendrie���m�́A����̌����́A���A�a���ÖA���c�n�C�}�[�a�̎��Âɗp���邱�Ƃ��ł���\���𗠂Â�����̂Ƃ��ĕ]�����Ȃ�����A�u�A���c�n�C�}�[�a�̊댯���q�Ƃ��ẮA�������≊�ǂȂǑ����̈��q������B���̂��߁A�����_�ŃA���c�n�C�}�[�a�A�a�Ȃǂ̓����厾���̘g�ɂ͂ߍ��ނ͎̂��������ł���ƍl����v�Əq�ׂĂ���B
�@����A�ăR�����h�B����w������w�Ȋw��������Douglas N. Ishii���́A���b�g�̌����ŁA�C���X�����l�������q�𒍓�����Ɗw�K�\�͂���ыL���͂̂�����̒ቺ���}���ł��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��Ă���A�C���X����������C���X�����l�������q���A���c�n�C�}�[�a�̐i�s��}����̂ɏd�v�Ȗ������ʂ����Ƃ݂Ă���B |
|
| �z���V�X�e�C�� |
���z���V�X�e�C�����^�E��A�����q�����J�j�Y������������ |
2007-03-16 -
�A���c�n�C�}�[�a�̃��X�N�t�@�N�^�[�ł��鍂�z���V�X�e�C�����x���ƃ^�E��A�~���C�h�O��̃^���p�N���iAPP�j���^���p�N���z�X�t�@�^�[�[2A�iPP2A�j�ɂ���ă����N����ƕ�����܂����BBiotoday |
|
|
�A���c�n�C�}�[�a�F���nj����̈�𖾁@���ꏗ�q�Z�勳�� |
���ꏗ�q�Z��i����s�j�̒��J�시�����i�U�P�j�����O�q���w�����S���A�A���c�n�C�}�[�a������҂ɑ������ǂ��郁�J�j�Y���̈���𖾂����Ɩ��炩�ɂ����B�V���ɂ���Đ_�o�זE�̓������}�������ƁA���a�������N���������u�z���V�X�e�C���_�v���]�̐_�o�זE�����������������邱�Ƃ������Ŏ������B���ǂ̎d�g�݂����m�ɂȂ��Ă��Ȃ����a�̎��Âɖ𗧂Ă����l���ŁA�������ʂ́A�U���ɕč��ŊJ�����F�m�Ǘ\�h�̍��ۉ�c�Ŕ��\����B���J�싳���͂O�T�N���z���V�X�e�C���_�̗L�Q�ȓ��������߂ē���B����̎����ł͘V���Ƃ̊W�͂����B�V�����i�݁A�_�o�זE�̓������キ�Ȃ�ƁA�z���V�X�e�C���_���זE���ɗL�Q������~�ς����A�ʂ̌��������Ƒg�ݍ��킳��邱�ƂōזE�����邱�Ƃ����������B�Ⴂ����ł́A�z���V�X�e�C���_�������Ă��A�L�Q�������~�ς���Ă��Ȃ��̂ŁA�_�o�זE���܂ł͋N���Ȃ��Ƃ����B���J�싳���ɂ��ƁA�r���̌���o�s�r�c�i�S�I�O����X�g���X��Q�j�Ȃǂ̋����X�g���X���A���c�n�C�}�[�a�̊댯���q�Ƃ���Ă���A�z���V�X�e�C���_�͂��̂悤�ȃX�g���X�������I�ɑ������ۂɑ�����B�@�@�@�@�����V���@2007�N3��5���@9��54�� |
|
| AchE |
�Β��̓A���c�n�C�}�[�a�̌����ƍl�����Ă������Z�N���^�[�[��j�Q���� |
2004-10-26 17:23:26 �Β���g���̓A���c�n�C�}�[�a�̔��a�E�i�s�Ɋւ��ƍl�����Ă����A�Z�`���R�����G�X�e���[�[(AChE)�Abutyrylcholinesterase (BuChE)�A���Z�N���^�[�[�̓�����j�Q�����p������ƕ�����܂����B2004�N8����Phytother Res���ɔ��\���ꂽ�������ʂł��B���ɁA�Β������Z�N���^�[�[�j�Q��p�͋��͂ł����B�g�������Z�N���^�[�[�j�Q��p��1�����������Ȃ��̂ɑ��A�Β������Z�N���^�[�[�j�Q��p��1�T�Ԏ������܂����B |
|
| �C���X���� |
�]���ł��C���X�������x�����ቺ����ƃA���c�n�C�}�[�a�̏����T�C���ł���_�o�זE�̕ϐ��������� |
2005-03-08 15:52:32 ���b�g�̎�������A�C���X�����Ƃ��̊֘A�����EIGF I/II�͔]���ō���Ă���A�]���ł̃C���X�������x�����ቺ����ƃA���c�n�C�}�[�a�̏����T�C���ł���_�o�זE�̕ϐ���������ƕ�����܂����B �܂��A�A���c�n�C�}�[�a���҂̔]�ׂ��Ƃ���A�C���X������IGF-�T�̃��x�����O���玿�A�C�n�A���������ŗL�ӂɒቺ���Ă��܂����B�����̗̈�͂��ׂăA���c�n�C�}�[�a�̔��a�Ɋ֘A������܂��B |
|
| ���A�~���C�h |
�������������̎d�g�݉𖾁��A���c�n�C�}�[�a�ŌF�{�� |
�F�{��w��w���̐����O������10���A�]���̉��ǂ��A���c�n�C�}�[�a��i�s������d�g�݂��𖾂����Ɣ��\�����B��������ς����u���A�~���C�h�v�̔�����}���鎡�Ö�ɂȂ���\��������Ƃ����B�l�̒��̉��ǗU�������́A�_�o�זE�̕\�ʂɂ����e�̂ƌ������Ċ���������B���������͉��ǗU�������u�v���X�^�O�����W��E2�v���A���킠���e�̂̂����uEP2�v�uEP4�v�ƌ�������ƁA���A�~���C�h�����𑣐i�����AEP4�̓�����}����j�Q����g���Ƌt�ɔ������}������邱�Ƃ������Ǔ��̎����Ŕ��������B��`�q����łQ�̎�e�̂������Ȃ��}�E�X���쐻�A����ȃ}�E�X�Ɣ�r�����Ƃ���A���A�~���C�h�̗ʂ������ȉ��Ɍ������B2007�N9��10��23��32���z�M �����ʐM |
|
| �C���X���� |
���A�a�͖��a�̂��Ɓ@�A���c�n�C�}�[���ǂS�D�U�{ |
���A�a�₻�́u�\���Q�v�̐l�́A�����łȂ��l���A���c�n�C�}�[�a�ɂȂ�댯�����S�D�U�{�������Ƃ��A��B��̐����T�����i����w�j��̌����ł킩�����B�������v�R���̏Z����W�O�O�l���P�T�N�ԁA�ǐՂ��ĕ��͂����B�����]�[�ǁi���������j�A�S���a�����a���₷���Ƃ����B���A�a���A�����Ȃǂ̍����ǂɉ����A�l�X�ȕa�C�̉����ɂȂ邱�Ƃ������сA���̑�̏d�v�������߂Ď����ꂽ�B ���͋v�R���łP�X�U�P�N����Z�����f�����āA�����K����̎��ƕa�C�̊W�������B���S�����ꍇ�ɂ͉�U�ւ̋��͂����߂Ă���B ���������͂W�T�N���_�ŁA�_�o�����Ȃǂ���������č����q���������̌����@�ւ̊�ŔF�m�ǂł͂Ȃ��Ɣ��f�����U�T�Έȏ�̂W�Q�U�l��ǐՁB�O�O�N�܂łɏW�߂��f�[�^�̉�͂�i�߂Ă����B �P�T�N�ԂɂP�W�W�l���F�m�ǂǂ��A�����X�R�l���A���c�n�C�}�[�a�������B�摜�����̂ق��A���S�����P�S�T�l�͂X���ȏ����U���Ċm��f�f�������B �����W�Q�U�l�ɂ��āA�u�h�E���̑�Ӕ\�͂ł���ϓ��\�ُ̈�������B�����K������Ȍ����Ƃ����Q�^���A�a�̕a���������������������t�O�D�P���b�g��������P�P�T�~���O�����ȏ��\�\�Ȃǂ̐l����A���c�n�C�}�[�a�����ƍ��킹�ĕ��͂����B����瓜�A�a�₻�̗\���Q�̐l�́A�ϓ��\�ُ�̂Ȃ��l�ɔ�ׂĂS�D�U�{�A�A���c�n�C�}�[�a�ɂȂ�댯�������������B ��������ɂ��ƁA�]�ɂ��܂��ăA���c�n�C�}�[�a�������N�����Ƃ���镨���́A�C���X���������y�f�ɂ���ĕ��������B�ϓ��\�ُ�̐l���C���X���������Ȃ��ꍇ�������A�����y�f������̂ŁA�A���c�n�C�}�[�a�̊댯�������܂�Ƃ����B ��U�Ȃǂɂ��m��f�f�Ɋ�Â����A���c�n�C�}�[�a�����ŁA����قǂ̋K�͂̂��̂͐��E�ł��Ⴊ�Ȃ��Ƃ����B �܂��A�ʂɂS�O�`�V�X�̖�Q�S�O�O�l���W�W�N����P�Q�N�ԒǐՂ��A���A�a�Ƃ���A�]�[�ǂȂǂƂ̊W�����ׂ��B���̌��ʁA���A�a�̐l�́A�����łȂ��l��肪�S�̊댯�����R�D�P�{�����A�]�[�ǂ��P�D�X�{�A�S�؍[�ǂȂNj������S�������Q�D�P�{���������B ��������́u���A�a�A���c�n�C�}�[�a�\�h�ɂȂ���\��������B�����ł͂����\���N�őϓ��\�Ɉُ킪����l�������łQ���A�j���łS�������Ă���A����}���K�v������v�Ƙb���BAsahi.Com |
|
| HSV-1 |
�P���w���y�X�E�C���X1�^�iHerpes Simplex Virus�AHSV-1�j�ƃA���c�n�C�}�[�a�̊֘A�������V���Ȍ������� |
���̒m���Ƃ���܂ł̌������ʂ���AHSV-1�����͓���ApoE4��L����l�̃A���c�n�C�}�[�a���X�N�����߂�댯������Ǝ�������܂����B�A���c�n�C�}�[�a�������l�̂��悻������ApoE4���F�߂��A���l�̖�30����ApoE4��`�q�^�����Ȃ��Ƃ���R�s�[�L���Ă��܂��B�܂��A���悻80���̍���҂�HSV-1��L���Ă��܂��B���������āAApoE4��HSV-1���A���c�n�C�}�[�a�̃��X�N�����߂�Ƃ���A����͔��ɑ傫�ȉe����^���Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B�}���`�F�X�^�[��w��Ruth Itzhaki�����q�g�]�זE��HSV-1�������������Ƃ���A�זE�������A�~���C�h�iA���j�^���p�N���̃��x�������I�ɏ㏸���܂����BA���̓A���c�n�C�}�[�a���҂̔]���ɔF�߂���V�l���̎�v�ȍ\�������ł��B�܂��AHSV-1�������������}�E�X�̔]���ɂ����Ă�A�������l�ɏ㏸���邱�Ƃ�Itzhaki���͊m�F���܂����iNeuroscience Letters, Article in Press�j�B ���̂��Ƃ���AHSV-1�̓A�~���C�h�^���p�N�������A�ŏI�I�ɃA���c�n�C�}�[�a���҂̔]�ɂ���V�l���������Ă���\���������Itzhaki���͌����Ă��܂��B�ʂ̎����ŃA���c�n�C�}�[�a���҂̎���]�ׂ��Ƃ���AHSV-1��L����A���c�n�C�}�[�a���҂̃A�~���C�h����HSV-1��DNA���t�����Ă��邱�Ƃ��m�F����܂����B���̌������ʂ�9���ɉp���̃P���u���b�W�ŊJ�Â��ꂽStrategies for
Engineered Negligible Senescence�̉�c�Ŕ��\����܂����B��N�A���`�F�X�^�[��w��Renee Miller���́AApoE4��L����}�E�X�ɂ�����HSV-1�͂�芈�����������Ƃ��������ʂ\���܂����iNeurobiol Aging. 2006 Nov 11�j�BItzhaki���́AApoE4��`�q�^��L����l�ɂ����Ă͐����������Ă���HSV-1�����x������������̂ł͂Ȃ����Ɛ������Ă��܂��B�ޏ��͍R�E�C���X��ɂ���Ă��̊��������X�g�b�v�ł��邩�ǂ����ׂ����ƍl���Ă��܂��B�܂��ޏ��͎��̂悤�Ɍ����Ă��܂��B�u�ŏI�I�ɂ́AApoE4��`�q�^��L����l�ɍRHSV-1���N�`�����������ɐڎ킷��悤�ɂȂ邩������Ȃ��B�v�������A�R�E�C���X���N�`���̗L�����͗Տ������ŐT�d�ɒ��ׂĂ����K�v������܂��B�P���w���y�X�E�C���X1�^�����������]�זE�ł�A������ʂɐ�����BBiotoday |
|
| HSV, CMV |
�E�C���X�ƔF�m�� |
�w���y�X�E�C���X���T�C�g���K���E�C���X�̃E�C���X���x�����������ƂƉƒ�ɏZ�ލ���҂̔F�m��Q���֘A���邱�Ƃ���������2004�N�ɔ��\����Ă��܂��B Biotoday |
|
| �^�E����� |
�u�V���ŕ��Y��v�̎d�g�݉𖾁��A���c�n�C�}�[�Ɠ�������ς����֗^�|���� |
�A���c�n�C�}�[�a�Ɋ֗^���邽��ς����̈���A�V���ɔ����L����Q�̌����ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��A�����w�������̍������F�A���c�n�C�}�[�a�����`�[�����[�_�[�炪�}�E�X���g���������Ŋm�F���A15���t�̊w��ɔ��\�����B���̂���ς������]���ɒ~�ς���ƁA�A���c�n�C�}�[�a�̌����ɂȂ�_�o�זE�̕ώ��i�_�o���@�ەω��j�������炷���A�����ɔ����ł���A���Ǘ\�h�����҂ł���Ƃ����B�l�Ԃ̔]�͘V���ɔ����A�L���̌`���ɂ������k����i���イ�Ȃ���j�Ƃ������ʂɁu�ߏ胊���_���^�E����ς����v���~�ς��A�_�o���@�ەω��������B���̌�u�x�[�^�A�~���C�h�iA���j�v�ƌĂ��ʂ̂���ς����ɂ��]�̍L�����ʂɐ_�o���@�ەω����g��A�A���c�n�C�}�[�a�Ɏ���B�����`�[���́A�q�g�̃^�E����ς��������}�E�X�i�^�E�}�E�X�j����`�q����ł������B�w�K�A�L���s���Ɛ_�o�זE�̊����ׂ��Ƃ���A�Ⴂ�^�E�}�E�X�ł͒ʏ�̃}�E�X�Ƃ̈Ⴂ�͂Ȃ��������A�V��ł͚k����̐_�o���@�ەω����N���Ă��Ȃ��Ă��A�L���\�͂��ɒ[�ɒቺ���Ă����B�V��^�E�}�E�X�̚k������ڂ������ׂ�ƁA�_�o�זE���m�̂Ȃ���i�V�i�v�X�j�̌����������B�^�E����ς������_�o���@�ەω��Ƃ͕ʂɁA�V�i�v�X�����������ċL����Q���N�����Ă��邱�Ƃ����������B�@�_�o���@�ەω��͌��ɖ߂��Ȃ����A�^�E����ς����͖�܂ŊQ��^���Ȃ���Ԃɕω������邱�Ƃ��ł��邽�߁A�����̔����ɂ��A�L����Q�̉��P��A���c�n�C�}�[�a�ւ̐i�s��h����\��������Ƃ����B�@11��16��2��30���z�M �����ʐM |
|
| �z���V�X�e�C�� |
HDL���x�����Ⴍ�A�z���V�X�e�C�����x���������A���A�a��L���銳�҂͔]������ɔF�m��Q��g�̏�Q�𗈂������X�N������ |
2007-12-01 -
�ߋ�3�����ȓ��Ɍy�x�`�����x�̔]�������������A�����J�E�J�i�_�E�X�R�b�g�����h��35�Έȏ�̒j��3680�l�̃f�[�^����͂������ʁA���A�a�̗L���EHDL�R���X�e���[���E�z���V�X�e�C���Ɣ]������̔F�m�@�\��g�̋@�\�]�A�̊֘A����������܂����BBiotoday |
|
| ���A�~���C�h |
�A���c�n�C�}�[�a�������N�������A�~���C�h���_�o�Ő��̋�������\�������V���Ȓ��ԑ̂��o�ĕs�t�I�Ȑ��ۍ\���ւƕϊ����邱�Ƃ� |
��Illinoi��w���w��NMR���{�̌����O���[�v�́A���A�~���C�h��A��1-40�y�v�`�h��p���ăA�~���C�h�`���ߒ��ׁA�Ő��̂Ȃ����m�}�[����A�Ő��̋����p���������V�[�g�\���̋��ԑ́iI���j���o�āA�ŏI�I�ɒ����q�\�����`����ɐ��ۂւƕϊ����邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B�ڂ����́A12����2�T���ɔ��s�����Nature Structural �� Molecular Biology���I�����C���Łi07�N12��2���t���j�Ɍf�ڂ��ꂽ�B |
|
| �A�~���C�h���`��1-42���^�E�`�� |
���������̂��߂̃o�C�I�}�[�J�[ |
�����w��w�@�ی��w��U�̉Y�㍎�Ƌ����́C�F�m�ǃX�N���[�j���O�̂��߂̃}�[�J�[�ƁC���̒i�K�̊m��f�f�Ɏg���o�C�I�}�[�J�[�Ƃɕ������������ʂ��������B�@1
���X�N���[�j���O�̂��߂̃}�[�J�[�Ƃ��āC�������̃O���[�v�̓^�b�`�p�l�����R���s���[�^��p�����F�m�ǃX�N���[�j���O�@���J���B3 �` 5
���Łu�P��ĔF�v�C�u�����̌������v�C�u����ԔF�m�@�\�v�� 3
���ڂ̌������s�����̂ŁC���������ł��ȒP�ɓ����ł���B�l������������e�X�g�Ő����������Ȃ��C�팟�҂̕��S�����Ȃ��B���ɒn��̔F�m�Ǘ\�h���f�ŁC�]���̃A���P�[�g��ʏ�̖�f�ł͌�������Ă��������̔F�m�ǂ���������Ă���B�@���݁C�m��f�f�̂��߂̃o�C�I�}�[�J�[�Ƃ��āC�A�~���C�h���`��1-42���^�E�`���̔䗦�Ȃǂ��L�p�Ƃ���Ă��邪�C�P�̂ł�萸�x�̍������̂Ƃ��ă����_���^�E�`�������x96���C���ٓx97���ƁC�L�p�����������Ƃ��킩�����B�������C
�A���c�n�C�}�[�a�iAD�j�ƃ^�E�I�p�`�[�Ƃ̊ӕʂ��ł��Ȃ��B���̂��߁C��������͐V���������Ƃ��ď�����背�N�`���iWGA�j�������`���ɒ��ڂ����������B���̒l�𑪒肷��ƁCAD�Ƃ��̑��̔F�m�ǂƂ̊ӕʂ��\�ł���Ƃ̃f�[�^�������Ă���B�@�������́C����̉ۑ�Ƃ��āu���t�����͈�ʓI�Ɏ��{�ł��Ȃ����߁C�A�⌌���Ȃǂ̊ȕւȃT���v����p���Đ��l�Ŕ���ł�����p���̍����o�C�I�}�[�J�[�̊J�����g���ƍl����v�Əq�ׂ��B |
|
| �^�E�`���� |
�^�E�`�����Z�x�ቺ�����Ð헪�Ɂ@���������ʼn\�������� |
�k�j���[���[�N�l �~�l�\�^��w�i�~�l�\�^�B�~�l�A�|���X�j��Karen H. Ashe���m�́C�Տ��I�ɈӋ`�̂����b�����̏�����t�ɒ��邱�Ƃ�ړI�Ƃ���New England Journal of Medicine�iNEJM�C2007;
357: 933-935�j�ɔ��\�����_���ŁC�u�^�E�`�����Z�x�̒ቺ�́C�A���c�n�C�}�[�a�iAD�j�Ɗ֘A�����̎��Â̗L���Ȑ헪�ł��邩�C���������̌��ʂ��q�g�ɓ��Ă͂܂�̂��Ƃ������^��͎c����̂́CScience�ɍŋߔ��\���ꂽ�����͎��Ð헪�̉\���ɔ����J�����̂ł���v�Əq�ׂĂ���B |
|
| �^�E�`���� |
�^�E�`�����Z�x�ቺ�ŋ@�\��Q��\�h |
�J���t�H���j�A��w�T���t�����V�X�R�Z�iUCSF�C�T���t�����V�X�R�j��Erik D. Roberson���m��́CScience�i2007; 316: 750-754�j�ɔ��\���������̂Ȃ��ŁC�������^�E�`�����Z�x�̒ቺ���q�g�A�~���C�h�O��̒`�����ihAPP�j������g�����X�W�F�j�b�N�}�E�X�ɂ�����s����Q��\�h���邱�ƁC���������̗\�h���ʂ͍����A�~���C�h�`�����Z�x��ω��������ɔ�������邱�Ƃ������C����ɁC�����f���}�E�X�ɂ�����^�E�`�����Z�x�̒ቺ���g�����X�W�F�j�b�N�}�E�X�C�쐶�^�i�`���]�����Ă��Ȃ��j�}�E�X�̂�����ł������Ő��̔�����}�����邱�Ƃ𗧏����B�����̒m������C�����m����^�E�`�����Z�x��ቺ�����邱�Ƃɂ��C���A�~���C�h�`�����U�����̐_�o�@�\��Q�Ƌ����őf�U�����̐_�o�@�\��Q��\�h�ł���ƌ��_�B���̎����̂��߂ɁCAPP���Y������ˑR�ψك}�E�X���C�^�E�`������`�q��s�����������}�E�X�ƌ�z�����C����}�E�X����x���̃^�E�`����������}�E�X����`�q����ɂ��쐻�����B�����m��͈ȑO�C�����̂��߂�APP���Y������ˑR�ψِe�}�E�X���J�����iMucke L, et al. Journal of
Neuroscience 2000; 20: 4050-4058�j�C����̎����p��hAPP�̕ψّ̂��Y������}�E�X���J�������B���̕ψّ̂́C�������Ƒ���AD�Ɋ֘A���� 2 ��̕ψق����� 1 �̈�`�q�ɂ��C�����̃}�E�X�ɃR�[�h���ꂽ�BAPP�́C�ؒf���������A�~���C�h�`������V������B�����m���2000�N�̎����̂��߂ɊJ�����ꂽ�}�E�X�́C����ɂ��s����Q�C�L���r���ƃA�~���C�h�������������̂́C�_�o�����ۉ�͌����Ȃ������B����ɁC2000�N�̎����ł́C�ꕔ�̃}�E�X�������ɓˑR�����Ă���B[2008�N1��10���iVOL.41 NO.2�j p.42]�@Medical
Tribune |
|
| �^�E�`���� |
����w�����c�����A�A���c�n�C�}�[�a�̘_���I�o�C�I�}�[�J�[���J�i�_PDI�ЂƘ_�����\�A�������̗Տ��]���Ɋ��p2008-01-23�@Biotechnology Japan |
�u�F�m�͂̉��P��]���ł��鐶���w�I�}�[�J�[�i�o�C�I�}�[�J�[�j�́A�K���Ȃ��̂��Ȃ��B10�N�قǑO���琑�t�����A�~���C�h���̌������^�E����ς����̑������AELISA�@�Œ�ʂ��Ă��邪�A��Ԃ̖��͕a�C�̒��x��d�Ǔx�Ƃ��܂葊�ւ��Ȃ����Ƃ��B���̂��ߖ��^�Ȃlj���̌��ʔ���ɂ��g���ɂ����B�ǂ������X�g���e�W�[�ŏd�Ǔx��c�����Ă������A���낢��ȍl����������B���^�{���[����͂ō���A1��₪���������v�����B�A���c�n�C�}�[�^�V�N�F�m�ǁiDAT�j�̊��҂ŁA�������̃G�^�m�[���A�~���E�v���X�}���[�Q���iPlsEtn�j�����R���邱�Ƃ��m�F�����Ƃ������ʂ��AJ.Lipid Research��07�N11�����iJ Lipid Res. 2007
Nov;48(11):2485-98.�j�ɘ_�����\��������w��w�n�����ȏ����w�u�����_��w�̕��c��r�����́ADAT�����P������ʂ����҂ł��鉻�����̗Տ��]���ŁA����PlsEtn�Ɋ��҂��Ă��邱�Ƃ����������B���̐��ʂ́A���a�@��07�N5���ɕ��g�����J�i�_Phenomenome Discovery
Inc.�ЂȂǂƂ̋��������̐��ʂ��B |
|
| �A�~���C�h���i�x�[�^�j�`�� |
�A���c�n�C�}�[�a�̃v���[�N��1���Ō`������� |
�킸��24���ԂŌ`������邱�Ƃ��A�p�Ȋw���uNature�v2��7�����ŕ��ꂽ�B�A�~���C�h���́A�A�~���C�h���i�x�[�^�j�`���i����ς��j���~�ς������̂ŁA�A���c�n�C�}�[�a���҂̔]�ɂ݂���B
�����𗦂����ă}�T�`���[�Z�b�c�����a�@�i�{�X�g���j�_�o�ϐ�������������Bradley
Hyman���m�ɂ��ƁA����܂ŁA�A���c�n�C�}�[�a�̓������f����p���������ɂ��A�������i�s����X�̒i�K�̒f�ГI�ȎB���͓����Ă����B����g�p�����������C���[�W���O�Z�p�ɂ���āA���̃v���Z�X���������̔]�ŏ��߂���I���܂ŏ���ǂ��Č��邱�Ƃ��\�ɂȂ�A���ǍזE������������Đ����邳�܂��܂Ȏ��ۂ��킩�����Ƃ����B��������A�~���C�h������������ƁA�ߕӂ̐_�o�זE���قڑ����ɑ������邱�Ƃ��킩�����B
Hyman����́A�A�~���C�h�����`������n���̃}�E�X��p���A���̌������C���[�W���O���ŏ��͏T1��A���̌�1��1����{�����B���̌��ʁA�v���[�N�̌`������r�I�܂�Ȏ��ۂł��邱�Ƃ��킩�����B�������A�ꕔ�̃}�E�X�ł́A�A�~���C�h���̌����Ȃ��摜���B������Ă���킸��24���Ԍ�ɁA�A�~���C�h�����F�߂�ꂽ�Ƃ����B
���̃A�~���C�h���`���}�E�X�ɋN���邱�Ƃ́A�قڊԈႢ�Ȃ��q�g�̔]�ɂ��݂���Ƃ����A�A���c�n�C�}�[�a���X�N�����l�ɂ��̒m����K�p���邱�Ƃ��ł����Hyman���͏q�ׂĂ���B�A���c�n�C�}�[�a�����ł́A�A�~���C�h���`�����悩�A�_�o�ϐ����悩���c�_�̑ΏۂƂȂ��Ă������A����̌�������A�v���[�N�̌`�����ŏ��̎��ۂł��邱�Ƃ����t����ꂽ�Ƃ����B�_�o�ϐ��������ŋN���邱�Ƃ��킩�����B
��A���c�n�C�}�[�a����iAA�j��Sam
Gandy���m�́A���̒m���̓A���c�n�C�}�[�a�̎��Ö@�J���ɒ��ڊ֘A������̂ŁA�R�A�~���C�h���Â����ɂ��Ȃ������̂ł��邱�Ƃ�����ɋ������t����ꂽ�Əq�ׂĂ���B�܂��A�A�~���C�h���͌��ǂ̋߂��ɂ̂`�������Ƃ̕��ߋ��ɂ��������A����̌������ʂ���́A���̂悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ����Ƃ��킩�����B
����A�A���c�n�C�}�[�a�̌����Ƃ����]�̕ϐ��́A�A�~���C�h���̌`�������ł͂Ȃ���Hyman���͏q�ׂĂ���B������̒��ڂ��ׂ������ɁA�]�̐_�o�זE�̍��i���Ȃ��^�E�`���itau protein�j�̕ϐ�������B����Ɠ����Z�p�𗘗p���āA�����^�E�`���̕ϐ��Ɋւ��錤�����܂��Ȃ��J�n�����\��Ƃ̂��ƁB2008�N2��6��/HealthDay News |
|
| �A�~���C�h�� |
���A���c�n�C�}�[���V�l���Ȃ��Ă����a�@���s��Ȃǔ��� |
�A���c�n�C�}�[�a�̊m��f�f�̎w�W�̈�ŁA���҂̔]�ɕK��������Ƃ���Ă����V�l���i�A�~���C�h���j���Ȃ��Ă��A���a����ꍇ�����邱�Ƃ���s����Ȃǂ̌����`�[�������������B�����������҂���́A����܂Œm���Ă��Ȃ�������`�q�̕ψق�������A���ǃ��J�j�Y���𖾂⎡�Ö@�J���ɂȂ���\��������B�Đ_�o���Ȋw���d�q�łɌf�ڂ��ꂽ�B�V�l���́A�A�~���C�h���Ƃ�������ς����������ɂȂ����Ăł���B�]�ɒ~�ς���ƁA�_�o�זE������ł��܂��A�L����Q�ȂǃA���c�n�C�}�[�a�̏Ǐo��Ƃ����B�x�R�M���E���s����y�����i�]�_�o�Ȋw�j�炪�A��N���A���c�n�C�}�[�a���҂̈�`�q�ׂ��Ƃ���A�A�~���C�h��������`�q�̈ꕔ���������Ă������B���̊��҂̔]�ɘV�l���͌����炸�A�A�~���C�h�����q�������������d���̂������������B�����`�[���̐X�[�E���勳���ɂ��ƁA�����̃A���c�n�C�}�[�a���҂̔]�ɂ́A�V�l���ƂƂ����A�~���C�h���̏d���̂�������B���b�g���g���������ł́A���̏d���̂��_�o�זE���m�̏��`�B��j�Q���A�F�m�ǂ̂悤�ȏǏ���N�����Ⴊ����Ă���Ƃ����B�X�����́u�A���c�n�C�}�[�a�́A�A�~���C�h���̏d���̂����邾���Ŕ��ǂ���\��������B�V�l���Ƀ^�[�Q�b�g���i�������݂̐f�f�⎡�Ö@���������K�v�������邩������Ȃ��v�Ƙb���Ă���B�y��ꂠ���z |
|
| A�� |
A����IL4�����郏�N�`���ڎ�Ń}�E�X�̃A���c�n�C�}�[�a���h���� |
2008-05-21 -
�A���c�n�C�}�[�a�̌��������ƍl�����Ă���A����2�^�w���p�[T�זE�lT�זE�����𑣂��T�C�g�J�C���E�C���^�[���C�L��-4�������q�g�w���y�X�E�C���X�iHSV�j�A���v���R���̃��N�`���ڎ�ɂ��A���c�n�C�}�[�a�}�E�X�̕a�����y�����A�s����w�K/�L���@�\�����P���܂����B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|